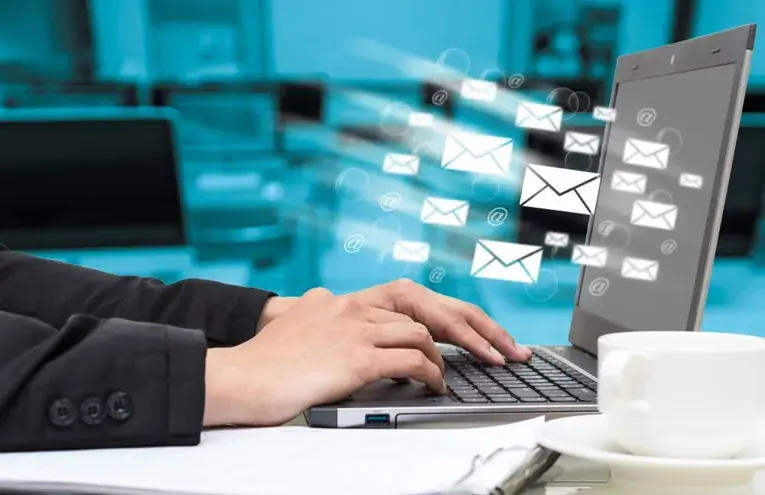情報漏えいは、企業にとって深刻な経営リスクの1つです。サイバー攻撃や内部不正、ヒューマンエラーなど、さまざまな要因が情報流出の原因となっています。本記事では、企業で実際に発生した情報漏えいの事例5選を紹介し、具体的な原因と対策を詳しく解説します。自社のセキュリティ対策を見直し、情報漏えいを未然に防ぎましょう。
会社・企業における情報漏えいとは何か

情報漏えいとは、企業が保有する機密情報や個人情報が外部に流出することを指します。
原因は、サイバー攻撃や内部不正、従業員のミスなど多岐にわたり、企業にとって大きなリスクとなります。ここでは、情報漏えいの定義や種類について解説します。
情報漏えいの定義と基本的な考え方
情報漏えいとは、企業の機密情報や個人情報が、許可なく外部に流出することを指します。
これは意図的な不正行為だけでなく、不注意によるミスやシステムの脆弱性を突いたサイバー攻撃など、さまざまな要因によって発生します。
情報漏えいは、以下の3つのパターンに分類されます。
- 外部からの攻撃:サイバー攻撃や不正アクセスによる情報流出
- 内部のミス:メールの誤送信や設定ミス、紛失などのヒューマンエラー
- 内部不正:従業員や関係者による意図的な情報持ち出し
企業にとって情報漏えいは、信用低下、経済的損失、法的責任といった深刻な影響をもたらすため、適切な管理が求められます。
会社・企業が管理する情報の種類
企業が管理する情報には、以下のような種類があります。
- 個人情報:顧客・従業員の氏名、連絡先、クレジットカード情報など
- 機密情報:事業戦略、財務データ、契約書、研究開発データなど
- 取引先情報:契約条件、未公開の事業計画、取引データなど
- システム関連情報:社内ネットワークのアクセス情報、パスワードなど
これらの情報が漏えいすると、企業の信用失墜や経済的損失だけでなく、取引先や顧客にも重大な影響を及ぼす可能性があります。
そのため、情報の適切な管理とセキュリティ対策の強化が不可欠です。
会社で発生する情報漏えいの主な原因

企業における情報漏えいは、外部からのサイバー攻撃、従業員の不注意、内部不正の3つの主要な要因によって発生します。
特に近年は、サイバー攻撃の高度化により、多くの企業が情報漏えいのリスクに直面しています。
外部からのサイバー攻撃
サイバー攻撃は、企業の情報漏えいを引き起こす最も深刻な要因の1つです。
攻撃者は、企業のシステムやネットワークの脆弱性を突き、不正アクセスやデータの窃取を行います。
◼️主なサイバー攻撃の手法
- フィッシング攻撃:偽のメールやWebサイトを利用し、従業員のID・パスワードを盗み取る
- マルウェア感染:ウイルスやスパイウェアを仕込んだファイルを開かせ、社内ネットワークに侵入する
- ランサムウェア:データを暗号化し、復旧のために身代金を要求する
- ゼロデイ攻撃:システムの脆弱性が修正される前に、その弱点を悪用して攻撃する
近年、サイバー攻撃はより巧妙化しており、標的型攻撃やサプライチェーン攻撃など、企業が防ぎにくい手口も増えています。
不注意によるヒューマンエラー
情報漏えいの大きな原因の1つが、従業員の不注意によるヒューマンエラーです。
意図的な不正ではなく、単純なミスや確認不足が原因で、機密情報が外部に流出するケースが多発しています。
◼️主なヒューマンエラーの例
- メールの誤送信:誤った宛先に機密情報を送ってしまう
- 添付ファイルの誤送信:本来送るべきでない情報を含んだファイルを添付する
- 書類やデバイスの紛失:社用PC、USBメモリ、紙の資料を置き忘れたり、盗難に遭ったりする
- アクセス権限の設定ミス:機密情報が不要な社員や外部関係者にも閲覧できる状態になってしまう
ヒューマンエラーは、業務の慣れや確認不足から発生しやすく、一度情報が流出すると取り返しがつかない事態になることもあります。
会社・企業関係者による内部不正
情報漏えいは外部からの攻撃だけでなく、社内の従業員や関係者による内部不正によっても発生します。
特に、退職予定の社員や不満を抱えた従業員が意図的に機密情報を持ち出すケースが問題視されています。
◼️主な内部不正の例
- 機密情報の持ち出し:営業データや顧客リストをUSBメモリやクラウドストレージにコピーして持ち出す
- 不正アクセス:退職後もアカウントが削除されず、元社員が社内システムにアクセスして情報を盗む
- 競合企業への情報提供:金銭や転職の見返りとして、自社の機密情報を競合他社に提供
企業の機密情報は、外部攻撃だけでなく、内部の人間によっても漏えいするリスクがあるため注意が必要です。
会社の情報漏えい事例5選

企業の情報漏えいは、サイバー攻撃や内部のミス、不正行為など、さまざまな原因で発生しています。
ここでは、実際に発生した情報漏えいの事例を5つ紹介し、それぞれの発生原因や影響について解説します。
ランサムウェア攻撃による情報漏えい
ランサムウェア攻撃とは、企業のデータを暗号化し、復旧と引き換えに身代金を要求するサイバー攻撃です。攻撃者は、メールの添付ファイルや脆弱なネットワーク経由でマルウェアを侵入させ、システムをロックします。
実際の事例として、2023年にKADOKAWAが海外拠点のサーバーに対するランサムウェア攻撃を受け、一部の業務に影響が出ました。幸い、顧客情報の流出は確認されませんでしたが、被害の範囲特定や復旧作業に多大なコストと時間を要しています。
このような攻撃は、企業の業務を停止させるだけでなく、機密情報が外部に流出するリスクも伴います。
個人情報の取り扱い不備
企業が適切な管理を怠ったことで個人情報が外部に流出するケースも、情報漏えいの大きな要因となります。特に、システムの設定ミスや誤ったデータ管理が原因で発生することが多く、企業の信頼を大きく損なうリスクがあります。
2024年、ファーストリテイリングは、社内システムの設定不備により、顧客の個人情報が外部から閲覧可能な状態になっていたと公表しました。この問題は、第三者からの指摘によって発覚し、該当する顧客に対して謝罪が行われました。
個人情報の取り扱いにおける不備は、企業の信用低下や法的責任につながる重大なリスクであるため、厳格な管理が求められます。
フィッシングサイトにアクセス
フィッシング詐欺とは、正規の企業やサービスを装った偽のWebサイトやメールを使い、個人情報や認証情報を盗み取る手口です。企業の従業員がフィッシングサイトにアクセスし、情報を入力してしまうことで、機密情報の漏えいにつながることがあります。
2023年、矢野経済研究所の従業員がフィッシングサイトにアクセスし、社内のメールアカウント情報が外部に流出しました。その結果、第三者による不正なメール送信が行われ、さらなる情報漏えいのリスクが発生しました。
このような被害は従業員の一瞬のミスで発生し、社内外に大きな影響を及ぼすため、注意喚起と対策の徹底が不可欠です。
SQLインジェクションによる顧客情報漏えい
SQLインジェクションとは、Webサイトの入力フォームなどに不正なSQL文を埋め込み、データベースから情報を不正取得する攻撃手法です。脆弱なシステムでは、顧客情報や機密データが外部に漏えいするリスクがあります。
2023年、スニーカーダンク(SNKRDUNK)は、SQLインジェクション攻撃を受け、一部の顧客情報が漏えいした可能性があると発表しました。攻撃者は、Webシステムの脆弱性を突いてデータベースへ不正アクセスし、顧客の個人情報を取得したとみられています。
このような攻撃は、システムの脆弱性を狙ったものであり、適切なセキュリティ対策が欠かせません。
脆弱性を悪用した不正アクセス
企業のWebサイトやシステムに存在するセキュリティの脆弱性を突かれると、不正アクセスによる情報漏えいが発生することがあります。特に、古いソフトウェアや未修正の脆弱性は攻撃の標的になりやすく、迅速な対応が求められます。
2022年、森永製菓の一部Webサイトに対し、脆弱性を悪用した不正アクセスが行われた可能性があると発表されました。これにより、サイトの利用者に影響が及ぶ可能性があり、同社は緊急で調査と対応を実施しました。
システムの脆弱性は、外部からの攻撃を招くリスクが高く、企業の信頼を大きく損なう原因となるため、適切な管理と定期的なセキュリティ更新が重要です。
会社・企業の情報漏えいを防ぐための対策

情報漏えいを防ぐためには、技術的・組織的・物理的な対策を組み合わせることが重要です。ここでは、セキュリティソフトの導入、社員教育、オフィスの管理強化など、企業が実施すべき具体的な対策を解説します。
技術的対策(セキュリティソフト導入・システム強化)
企業の情報漏えいを防ぐには、技術的なセキュリティ対策の導入が不可欠です。
特に、外部からのサイバー攻撃や内部の情報漏えいリスクを最小限に抑えるため、システムの強化が求められます。
◼️主な技術的対策
- セキュリティソフトの導入:ウイルス対策ソフトやファイアウォールを活用し、不正アクセスを防ぐ
- エンドポイント管理:社用PCやスマートフォンのセキュリティを一元管理し、異常な挙動を検知する
- データ暗号化:顧客情報や機密データを暗号化し、不正取得された際の情報漏えいリスクを低減
- ゼロトラストセキュリティの導入:全てのアクセスを検証し、信頼できる通信のみを許可
これらの技術的対策を適切に組み合わせることで、情報漏えいのリスクを大幅に軽減できます。
組織的対策(情報セキュリティポリシー・社員教育)
情報漏えいを防ぐためには、企業全体でセキュリティ意識を高め、適切な運用ルールを整備することが重要です。特に、従業員の知識や意識の不足が原因で発生する情報漏えいを防ぐために、組織的な対策が求められます。
◼️主な組織的対策
- 情報セキュリティポリシーの策定:社内で情報の取り扱いルールを明確にし、従業員に周知する
- アクセス権限の管理:業務に必要な情報のみ閲覧・編集できるよう、権限を適切に設定する
- 社員教育・セキュリティ研修の実施:定期的な研修を行い、最新のセキュリティリスクや対策を共有する
- インシデント対応計画の整備:情報漏えいが発生した場合に迅速に対応できるよう、対応手順を事前に策定
これらの対策を継続的に実施することで、企業のセキュリティ意識を向上させ、情報漏えいリスクを低減できます。
物理的対策(オフィスのセキュリティ・デバイス管理)
情報漏えいは、デジタルだけでなく物理的な管理の甘さによっても発生します。
特に、社内の重要情報が記録されたデバイスの盗難や紙資料の取り扱いミスが原因で、機密情報が外部に流出するリスクがあります。
◼️主な物理的対策
- 入退室管理の強化:ICカードや生体認証を活用し、オフィス内への不正な立ち入りを防止
- 機密情報の持ち出し制限:USBメモリや外部ストレージへのデータ保存を制限し、不正な持ち出しを防ぐ
- 書類の適切な管理と廃棄:機密情報を含む紙の書類は施錠管理し、不要になったものはシュレッダーで処理
- 社用デバイスの盗難・紛失対策:ノートパソコンやスマートフォンには遠隔ロック・データ削除機能を設定
物理的なセキュリティ対策を徹底することで、オフィス内外での情報漏えいリスクを軽減できます。
DLP(データ漏えい防止)の活用で会社・企業の情報を守る

DLP(データ漏えい防止)は、機密情報の不正流出を防ぐためのセキュリティ対策です。
企業の重要データを保護するために、DLPの仕組みや導入のメリットを理解し、適切に活用することが求められます。
DLP(データ漏えい防止)の概要と重要性
DLP(Data Loss Prevention)とは、企業の機密情報が外部に流出するのを防ぐためのセキュリティ対策です。
社内ネットワークやクラウド環境におけるデータの流れを監視し、不正な持ち出しや送信を防止します。
◼️DLPの主な機能
- データの識別と分類:機密情報を自動検出し、適切な保護措置を実施
- 情報の不正送信防止:メールやクラウドストレージへの不正なアップロードをブロック
- デバイス制御:USBメモリや外部ストレージへのデータコピーを制限
- ログ管理と監視:情報の取り扱い履歴を記録し、異常な操作を検知
企業の情報漏えいリスクを軽減するために、DLPの導入は非常に有効なセキュリティ対策の1つといえます。
DLP導入によるメリットと注意点
DLPを導入することで、企業の機密情報を適切に管理し、情報漏えいリスクを大幅に軽減できます。DLPは、データの流れを監視し、不正な持ち出しや外部送信を防ぐことで、サイバー攻撃や内部不正による情報漏えいのリスクを抑えることが可能です。
一方で、DLPの導入にはいくつかの課題もあります。例えば、誤検知により正当なデータ送信がブロックされる可能性があり、業務の妨げになることがあります。そのため、企業ごとに適切な設定を行い、柔軟な運用が求められます。
また、DLPの導入・維持にはコストがかかるため、企業の規模や業務内容に応じた適切な選定が必要です。そして、従業員がDLPの重要性を理解し、適切に運用するための教育やルールの周知も忘れてはいけません。
情報漏えいが発生した際の対応策

企業で情報漏えいが発生した場合、迅速な初動対応が被害拡大を防ぐ鍵となります。
ここでは、情報漏えい発覚後に取るべき対応として、初動対応・関係者への報告・再発防止策の策定について詳しく解説します。
情報漏えい発覚後の初動対応
まずは、漏えいの事実を確認し、流出した情報の種類や影響範囲の特定が必要です。具体的には、アクセスログの解析や関係者へのヒアリングを行い、正確な情報を収集します。
次に、流出した情報の悪用を防ぐため、該当するシステムの一時停止やアクセス制限を検討します。加えて、社内の緊急対応チームを立ち上げ、対応方針を迅速に決定することが求められます。
初動対応が遅れると、情報が拡散し、企業の信用低下や法的責任の発生につながりかねません。事前にインシデント対応マニュアルを整備し、迅速な対応ができる体制を構築しておくことが重要です。
関係者への報告と公表
情報漏えいが発生した場合、関係者への迅速かつ適切な報告が求められます。
特に、顧客や取引先の情報が流出した際は、影響を受ける関係者に対して正確な情報を伝え、適切な対応策を講じることが必要です。
まず、社内の管理部門や経営層に状況を共有し、報告内容や公表の方針を決定します。その後、被害を受ける可能性のある顧客や取引先に対し、メールや公式発表を通じて事実を報告し、対応策を説明します。
報告の遅延や不適切な対応があると、さらなる信頼低下を招くため、透明性のある対応が不可欠です。
再発防止策の策定と実施
情報漏えいが発生した後は、同じ問題を繰り返さないために具体的な再発防止策を策定・実施することが重要です。まず、漏えいの原因を特定し、技術的・組織的・人的な課題を洗い出します。
原因の分析が完了したら、社内のセキュリティ対策を見直し、必要な改善策を講じます。
例えば、サイバー攻撃が原因であれば、システムの脆弱性を修正し、セキュリティソフトを強化します。ヒューマンエラーが原因であれば、従業員への教育や社内ルールの改訂を行います。
情報漏えいは企業の信頼を大きく損なうリスクがあるため、一度発生した問題を教訓とし、長期的な視点でセキュリティ体制を強化することが不可欠です。
まとめ
情報漏えいは、サイバー攻撃・ヒューマンエラー・内部不正など、さまざまな要因で発生し、企業の信用や経営に大きな影響を与えます。実際の事例をもとに、情報漏えいのリスクと対策を理解し、自社のセキュリティを見直すことが重要です。
特に、DLP(データ漏えい防止)は、企業の情報資産を守るために有効な対策の1つです。
より詳しい対策方法や事例については、「情報漏えいの脅威に備える 実例と対策から学ぶDLP活用」をご覧ください。
- カテゴリ:
- サイバーセキュリティ